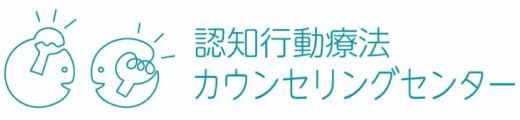2025年09月17日
- 認知行動療法
静岡浜松で母子分離不安へのカウンセリング

こんにちは。認知行動療法カウンセリングセンター静岡浜松店です。
私たちは、浜松市中央区を拠点に、地域の皆さまが安心してご相談いただける場を提供し、**認知行動療法(CBT)**を専門にしたカウンセリングを行っています。
今回のテーマは「母子分離不安」。
「子どもが登園や登校を嫌がる」「お母さんから離れると泣き出してしまう」「外出や就寝時に親がいないと強い不安を訴える」――このような悩みを抱えるご家庭は少なくありません。
母子分離不安は、決して珍しいものではなく、多くの親子が直面する自然な課題です。ただし、不安が長く続いたり強く出たりする場合には、本人やご家族の日常生活に大きな負担となることもあります。
本記事では、母子分離不安の特徴や原因、そして当センターで実践している認知行動療法によるカウンセリングについて、分かりやすくご紹介します。
母子分離不安とは?
母子分離不安とは、子どもが母親や家族と離れる場面で強い不安や恐怖を抱き、それが日常生活に影響を及ぼす状態を指します。
成長の一時期に「お母さんと離れるのが不安」という気持ちが表れるのは自然なことですが、これが長期間続いたり、強すぎて登園・登校や生活に支障が出る場合には、専門的なサポートが役立ちます。
よく見られる行動の例
- 保護者が見えなくなると泣き叫んで探す
- 「お母さん(お父さん)がいなくなるのでは」と強い不安を感じる
- 幼稚園や学校に行くことを拒否する
- 外出や就寝の際、家族がそばにいないと落ち着かない
こうした行動は、子どもが安心を求めているサインであり、親を困らせようとしているわけではありません。
母子分離不安の背景にあるもの
母子分離不安は、一つの原因だけで生じるわけではなく、いくつかの要因が重なって強まることが多いとされています。
- 気質や遺伝的要素
不安を感じやすいかどうかは、生まれ持った気質の影響を受けることがあります。 - 生活の変化や喪失体験
引っ越し、進学、離婚、親しい人との死別など、大きな環境の変化は不安を強める要因になります。 - 日常の関わり方や環境
親子の関係や生活リズムも、不安の強さに影響することがあります。
ただし、これは「育て方が悪い」という意味ではありません。むしろ、子どもの気質や環境が重なり合う中で自然に不安が強まることがある、という理解が大切です。
不安を乗り越える力を育むために
不安を感じること自体はごく自然な反応です。特に幼少期の子どもにとって、大人の存在は大きな安心材料です。そばで支えてもらう経験は「守られている」という感覚を与え、その後の成長に欠かせない土台になります。
安心感の積み重ねが大切
子どもが不安を覚えたときに「大丈夫だよ」と受け止めてもらえることは、とても大切です。安心できる体験を積み重ねることで、子どもは少しずつ自分の中に「大丈夫」という感覚を育てていきます。
安心と挑戦のバランス
一方で、「常に親がそばにいないと落ち着けない」という状態が長く続くと、不安を自分で扱う経験の機会が減ってしまいます。そのため、安心を十分に与えることと少しずつ自分で不安に向き合う練習をすることの両方が大切です。
実践の工夫例
- 「必ず戻ってくるよ」と伝えたうえで、短い時間だけ部屋を離れる
- 数秒でも一人で待てたら「よく頑張ったね」と褒める
- 徐々に「待てる時間」や「一人で過ごせる場面」を増やす
- 離れるときには「いなくなるのではなく、また戻る」というメッセージを繰り返し伝える
こうした小さな成功体験の積み重ねによって、子どもは「一人でも大丈夫かもしれない」という力を自分の中に育てていきます。
成長の両輪として
親がそばで安心を与える時間と、子どもが自分で不安に立ち向かう時間。どちらも欠かすことのできない大切な経験です。この二つをバランスよく取り入れることが、子どもの心をよりしなやかに、豊かに育てる支えになります。
母子分離不安のカウンセリング
母子分離不安への対応では、「できないことを無理に克服させる」のではなく、「すでにできていることを見つけて伸ばす」という視点がとても大切です。子どもが「一人でもなんとか対応できた」という体験を重ねることが、安心感や自信につながっていきます。
1. できている瞬間を見逃さない
まず最初に行うのは、家庭の中で「すでに一人で過ごせている瞬間」を探すことです。
たとえば、お母さんがトイレに行っている間、子どもは数秒でも一人で遊んでいられるかもしれません。その場面を見逃さずに、
「〇秒も一人で過ごせたね!すごいね!」
と子どもに具体的に伝えます。
2. 子どもと家族のニーズを確認する
次に「これからどうなりたい?」と子ども自身の希望を確認します。
「もっと挑戦したい」「少し長く待てるようになりたい」など、子どもが自分で方向性を考えることが重要です。
同時に「ご家族としてはどうなってほしいですか?」と保護者のニーズも確認します。子どもと家族の思いが自然に一致している場合、無理のない形で分離練習を進めることができます。
3. 段階的な分離練習
「離れることはいなくなることではなく、必ず戻ってくる」というメッセージを繰り返し伝えながら、数十秒ほど保護者にその場を離れてもらいます。
その間、子どもには好きな遊びや活動をして過ごしてもらいます。楽しい体験と「一人でいられること」が結びつくようにするのがポイントです。
4. 経験を共有し、達成を喜び合う
練習が終わったら、家族でその経験を一緒に振り返ります。
- できた場合 → 「やったね!今日は〇秒できたよ」と達成を喜び合う
- 途中で不安が強くなった場合 → 「最初の30秒は頑張れたね」とできた部分を評価する
こうして「できたこと」に目を向けることで、子どもは安心して次の挑戦につなげられるようになります。
5. 自発的な成長につながる
このプロセスを繰り返していると、子ども自身が「次はこれをやってみたい」と自発的に提案してくることがあります。これは、不安をただ避けるのではなく、自分の力で向き合う準備が整ってきたサインです。
カウンセリングのポイント
- できないことを直そうとするのではなく、できていることを見つけて伸ばす
- 安心感と挑戦をバランスよく取り入れる
- 「信じ合う関係」が前進の力になる
母子分離不安の改善には、子どもと家族の「小さな成功体験の積み重ね」が欠かせません。認知行動療法では、この成功体験を意識的に育てながら、不安を少しずつ「安心」に変えていくことを大切にしています。
静岡浜松で母子分離不安に悩むご家庭へ
母子分離不安は「問題」ではなく、成長の一過程でもあります。
ただし、不安が強すぎると本人やご家族にとって大きな負担となるため、早めのサポートが安心につながります。
認知行動療法カウンセリングセンター静岡浜松店では、親子それぞれのペースを尊重しながら「不安を安心に変える」ためのお手伝いをしています。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 母子分離不安は自然に治りますか?
A. 成長とともに落ち着く場合もありますが、強く長く続くと学校や家庭生活に影響が出るため、早めの相談がおすすめです。
Q2. 忙しくて十分に寄り添えないのですが大丈夫でしょうか?
A. 短い時間でも「安心できる関わり」を意識することが大切です。限られた時間の中でできる工夫をご一緒に考えます。
Q3. 他の兄弟姉妹への影響はありますか?
A. あります。分離不安のある子どもに多くの時間を割くことで、他の兄弟姉妹が孤独感を覚えることもあります。当センターでは、ご家庭全体を支える視点を大切にしています。
静岡浜松店のご案内
認知行動療法カウンセリングセンター静岡浜松店
〒430-0944 静岡県浜松市中央区田町231番地8 プレイスワン田町301号室
アクセス:遠州鉄道 遠州病院駅 徒歩3分、第一通り駅 徒歩4分
営業時間:10:00〜20:00(完全予約制)