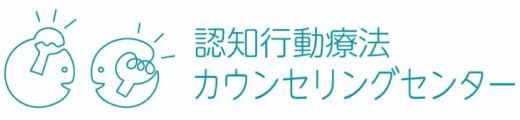2025年10月22日
- 認知行動療法
認知行動療法は何に効果があるのか!? / 認知行動療法カウンセリングセンター静岡浜松店

こんにちは。認知行動療法カウンセリングセンター静岡浜松店です。
当センターでは、認知行動療法という「考え方・感情・行動、そして身体の反応」に着目した心理支援を行っています。
日常のつらさは、出来事そのものではなく、その背景にある“こころと身体の動きのつながり”によって続くことがあります。
この流れを丁寧に整理し、扱いやすい状態へ整えていくことを大切にしています。
本日のテーマは
「認知行動療法は何に効果があるのか?」
です。
1.認知行動療法の目的
認知行動療法は「不安」「緊張」「落ち込み」「確認癖」「回避」「人間関係のぎこちなさ」といった心の反応が どのような仕組みで続いているのか を明らかにし、少しずつ扱いやすい状態へと近づけることを目指す心理支援です。
ポイントは、
「無理に変える」のではなく
「扱い方を増やしていく」という考え。
心の反応そのものを“良い/悪い”と判断しないことも特徴のひとつです。
2.認知行動療法は「何に」働きかけるのか
2.「どこに」働きかけるのか:4つの視点
私たちの中で起きている出来事を整理すると、おおまかに次の4つの要素が絡み合っています:
- 状況(出来事):例)「会議で発言を求められた」
- 認知(受け取り方・考え):例)「うまく言えなかったらどうしよう」
- 感情(感じていること):例)「不安・緊張・焦り」
- 行動/身体反応:例)「声が震える/黙ってしまう/緊張で動けない」
認知行動療法では、このうち特に “認知” と “行動” に焦点を当てます。
感情や身体反応も大切ですが、そうした反応を「思考/振る舞い」の面から少しずつ整えていくことで、「どう感じるか」「どう身体が反応するか」の影響を和らげていくという考え方です。
例えば、
すれ違った知人に目を向けられなかった時、「嫌われているかもしれない」と考え(認知)、不安に駆られ(感情)、心臓がドキドキし(身体)、足早に家へ帰ってしまった(行動)――このようなサイクルを整理・確認することから始まります。
このように「認知→感情→身体→行動」の流れを視野に入れることで、どこにアプローチすれば変えやすいかが見えてきます。
3.日常生活での“よくある例”
例えば職場の会議、地域の集まりやコミュニティ活動など「人前で話す」場面もあります。
このようなときに生じる“緊張”は自然な反応ですが、
- 頭が真っ白になる
- 声が震える
- 視線が怖い
- 目線を上げられない
- うまく笑えない
などの感覚が積み重なると、「また同じことが起きるのではないか」という警戒が強まり、場面自体を避けたくなることがあります。
ここに認知行動療法が関わると、
「なぜこうなるのか」
「続いている背景」
「自分の中で起きている仕組み」
が少しずつ明確になり、無理なく扱える範囲から調整しやすくなります。
4.“誤解されやすい点”
- 心を“鍛える”ものではない
- 耐える練習ではない
- ポジティブに無理やり変えるものではない
- 「根性論」とも違う
- 「瞬間的に不安が消える魔法」とも違う
認知行動療法は、 不安を“なくす”のではなく、不安と“付き合える幅を広げる” 支援と言えます。
この姿勢が、実務的にも相談しやすいと感じられる方が少なくない印象です。
5.認知行動療法が役立つ領域
認知行動療法は「特定の病名に対応するもの」というよりも、感情と行動のつながりが強く働く場面に合っています。相談のきっかけはさまざまですが、大きく分けると次のような領域があります。
① 不安・心配グセが離れないとき
- つい最悪の想定に意識が向かう
- 同じ考えが頭の中でぐるぐる回る
- 眠っても思考が続いてしまう
- 先の予定を考えるだけでも落ち着かない
「考え続けて何とかしようとする」ほど心配が強まり、心が休まらないサイクルが生じることがあります。認知行動療法では、この“心配を燃料にして延び続ける循環”を可視化し、「どう関われば距離がとれるか」を一緒に整えていきます。
② 人前での緊張や視線のつらさ
- 会議・スピーチ・朝礼・自己紹介
- オンライン会議での映りや声
- 自分の表情が固まる感覚
- 話す前から身体がこわばる
「失敗できない」「注目されると固まる」という反応には、思考・身体・行動の結びつきが濃く働きます。認知行動療法では、ここを小さなステップに分けて“緊張を扱える幅”を広げていきます。
③ 気分の落ち込み・停滞感
- 起き上がれないほどの落ち込み
- 意欲が湧かない
- やらなきゃと思うほど動けなくなる
- 何を始めても続けられない
ここでは「気分 → 活動量 → 自己評価」の相互作用を整理し、気分そのものを押し上げようとするのではなく、活動の幅を整え直す視点が用いられます。
④ 確認・安心を求めるクセ
- 何度も同じことを確認してしまう
- ミスや漏れがないか過剰に気になる
- “安心が切れる”と再び確認
- 人に保証を求め続ける
人に保証を求める行動は一時的に安心をもたらしても、長い目で見ると確認回数が増え、逆に不安が育ちやすくなることがあります。認知行動療法では「今すぐの安心」ではなく「扱える幅の回復」を視野に入れます。
⑤ 自分責めのクセ・評価への過敏さ
- 少しの失敗で極端に落ち込む
- 他人の目や反応に振り回される
- 頭ではわかっていても切り替えられない
- 自分だけ厳しく採点してしまう
ここでは「考え方のクセに気づき、別の光の当て方を増やす」ことが中心になります。
6.「環境を変える」前に「心の仕組み」を理解する
支援の場では「職場を変えれば良いのでは?」「環境調整で解決できるのでは?」という視点が語られることがあります。
もちろん環境が要因になることは少なくありませんが、環境を変えても同じ困りごとが繰り返されるケースもあります。
認知行動療法では、まず
✅ “なぜそうなるのか”
✅ “何が心のブレーキになっているのか”
✅ “どんな仕組みでつらさが続いているのか”
を見つめます。
環境より前に「心の使い方」そのものが整うと、
環境への感じ方・受け取り方・距離の取り方も変わっていきます。
7.“変える”のではなく“育てる”という視点
認知行動療法は、
「性格を変える」でも「考えを完全に切り替える」でもありません。
それよりも、
- 気づかなかった心の習慣に気づく
- 自分の内側にある選択肢を増やす
- 今ある反応を持ちながらもう一枚幅をつくる
- “こうしかない”を“こういう形もあり”へ
という “幅を育てる” 支援に近いものです。
このスタンスが、「無理をしない/でも停滞しない」状態を作りやすくします。
8.よくあるQ&A
Q1.どのくらい通えば良いですか?
通う期間は人によって異なります。
「回数」ではなく “変化のきっかけ” を一緒に見つけることが大切であり、回数設定を固定するのではなく、その人のペースを重視しています。
Q2.話を聞くだけでも良いですか?
もちろん可能です。
認知行動療法には「やり方」だけでなく「整理する過程」そのものに意味があります。話すことで見えてくる素材もあるため、無理に進めることはありません。
Q3.医療機関に通っていても利用できますか?
併用は可能です。
当センターは診断や薬に関わらない形で行いますので、医療機関と役割が重なることはありません。並行して利用されている方も少なくありません。
9.お申込・お問い合わせ
静岡浜松店は完全予約制のプライベートスペースで、オンライン・対面どちらにも対応しています。
【所在地】
〒430-0944 静岡県浜松市中央区田町231番地8 プレイスワン田町301号室
遠州鉄道 遠州病院駅 徒歩3分/第一通り駅 徒歩4分
【営業時間】
10:00〜20:00(完全予約制)
【WEB】
https://hamamatsu.cbt-mental.co.jp/
【LINE】
https://lin.ee/26sKHRK8
【お申込フォーム】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelm3nMBwOyvwnkhrkihe-APBzNTll2NL4fsPB6b6hHMzC8GA/viewform
10.まとめ
認知行動療法は、「心の働きを整える」というよりも
“自分の中に選べる道筋を増やす” 支援 です。
不安・落ち込み・緊張・確認・人間関係のぎこちなさなど、
日常のふとした瞬間に戸惑いが生まれる場面で、
「どう向き合うか?」の幅を取り戻す方法として用いられています。
何かをがらりと変えるよりも、
“その人に合った使い方”を一緒に育てていく ――
それが当センターにおける認知行動療法の基本姿勢です。
心が重たい時こそ、一人で抱え込むより
「まず整理すること」から始める方が進みやすくなることがあります。
もし迷われている場合は、一度ご相談ください。
一覧に戻る