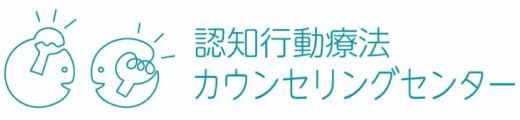2025年10月23日
- 認知行動療法
やるべきことをやらない人はなぜ動かないのか/認知行動療法カウンセリングセンター静岡浜松店

― 無責任に見える行動の正体と関わり方(実行機能の視点から)
「やるべきことをやらない」「無責任に見える」「叱っても動かない」背景には“実行機能”の問題が隠れていることがあります。周囲が疲弊せずに関わるための仕組み化・外部構造の整え方を心理職の視点から解説します。
こんにちは、認知行動療法カウンセリングセンター静岡浜松店です。
やるべきことをやらない人と関わると、周囲は大きく消耗します。
依頼しても動かない・反省しているようで改善しない・指摘しても繰り返す。
表面だけを見ると「無責任」「やる気がない」「甘えている」と見えて当然です。
しかし臨床的には、多くの場合この行動は意欲や人格の問題ではなく、「認知 → 行動」への橋渡し機能(実行機能)が脆弱なために生じる現象です。
つまり、「わかっている」状態から「行動へ変換する」工程が脳内で自動展開されません。
なぜ動かないのか ― 「実行できない」脳内プロセス
① 悩んでいないのではなく「悩みが保持されない」
・問題意識はその場では立ち上がる
・しかし保持されない
・行動へ転写されず消えていく
そのため、「危機感がないように見える」「反省が薄いように見える」のです。
② 説得・叱責が効かないのは“抽象で止まる”から
言葉は届いています。
しかし脳内で「行動計画」に翻訳されないため、翌日にはゼロに戻ります。
届いていないのではなく
“届いても処理されない”
「言われた瞬間はわかっている」のに反復が起きない理由です。
③ 性格ではなく「構造的な行動変換の断絶」
外側からはこう見えますが
| 外側の印象 | 内部プロセス |
| 無責任・怠惰 | 行動プロセスが生成されない |
| 反省がない | 反省→行動の接続不全 |
| やる気がない | 起動条件が内部にない |
→ 人格ではなく、プロセスの欠落(実行機能の弱さ)
関わる側がしんどくなる理由
① 支援疲労(“背負っている状態”)が生じる
・助けても変わらない
・代わりに背負う形になる
・良心が人質に取られる感覚
・結局こちらへ問題が戻ってくる
これは“優しさの問題”ではなく役割が偏っていることによる消耗です。
② 「背負う or 見捨てる」の二択の罠
どこかで支える側は、
耐えるか、突き放すか
の二択に追い詰められます。
しかし、本来必要なのは第三の道――
背負わずに“仕組みに委ねる”
支え方を変えるのではなく、“支える構造”を変える選択です。
実践的な関わり方(ケース別)
ケース1:返済・お金の問題
NG:意志や反省に期待
有効:日付・金額・方法まで“外部化”→「考える」でなく「選ぶ」
ケース2:仕事の締切・自発性の欠如
NG:「主体性を持って」「早めに」
有効:開始行動の明示+途中経過の可視化→トリガーで着火
ケース3:家事・生活面
NG:「気づいたらやって」
有効:完了ではなく“開始”を定義+摩擦除去+視覚保持
ケース4:連絡・報告が途絶える
NG:「なぜ返信しない?」
有効:報告を“作業の一部”に設計、テンプレ化、非同期記録化
Q&A
Q1. どこまで支えるべき?
→ 支える/放置ではなく「仕組みに委ねる」への切替えが境界。
Q2. 反省は演技?
→ 反省はあるが保持されない=行動に接続しないだけ。
Q3. 甘やかしとの違いは?
→ 代行は甘やかし、道筋を外部に置くのが構造支援。
まとめ
やるべきことをやらない人は、
“気持ちがない”のではなく 行動への変換プロセスが途切れている 状態です。
そのため必要なのは、叱咤や説得ではなく
外部の仕組みによる行動プロセスの補完
これにより、支える側の過剰負担も軽減し、関係性の消耗を防ぐことができます。
【各種リンク】
📍 静岡浜松店(公式サイト)
https://hamamatsu.cbt-mental.co.jp/
📩 予約フォーム
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelm3nMBwOyvwnkhrkihe-APBzNTll2NL4fsPB6b6hHMzC8GA/viewform
💬 LINE(相談・初回案内)
https://lin.ee/26sKHRK8