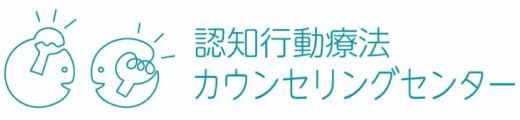2025年10月20日
- ご案内
NHKスペシャル取材協力のご報告と、再犯防止の視点/認知行動療法カウンセリングセンター静岡浜松店

性犯罪の再犯防止について、公に相談できる場所は決して多くありません。
「誰にも知られたくない」「相談先が分からない」まま、悩みを抱え込み続けている方も少なくありません。
今回、当センターはNHKスペシャルの取材協力を行いました。テーマは 「加害の“扉”が開くとき 子どもを守るには」──行動そのものではなく、扉が開く“手前”で何が起きているのか、という視点です。
当センターの支援もまさにこの“扉の前段階”に焦点を当てています。
「再犯を止める」だけでなく、そもそも扉を開かせない・開きかけている時点で踏みとどまれる状態を整えること。
この考え方が、再犯防止だけでなく、将来、子ども自身が“加害側に回らない”ための社会的予防にもつながります。
ご挨拶
こんにちは。認知行動療法カウンセリングセンター静岡浜松店です。
静岡浜松は都市部に比べると、こうした相談を周囲に打ち明けることが難しい地域性があります。そのため、外部ではなく「まずは安全で話せる環境」が必要と考えています。
当センターでは、公的立場からの“指導”ではなく、心理的支援として「なぜその扉に手をかけてしまうのか」「どこから立て直せるのか」を一緒に整理していきます。
性犯罪は“意思の弱さ”では説明できない
――「扉が開く」までに起きている流れ
性犯罪は「やめたいのにやめられない」「分かっているのに頭から離れない」など、本人自身も説明しづらい入り口から進んでいきます。そこには必ず“扉が開くまでのプロセス”があり、主に以下の4つの要素が絡み合います。
① 衝動(瞬間の強さ)
行動の最終段階には、非常に強い衝動が伴います。
「今すぐ」「逃したくない」といった感覚が前に出て、理性よりも一時的な欲求が優位になります。
② 習慣化された行動パターン
行為が繰り返されると、「特定の場所・時間・心の状態」がスイッチになりやすくなります。
“条件が揃うと同じ方向へ進みやすい”という現象です。
③ 考え方のゆるみ(自己正当化)
行動の手前では、判断感覚が緩みやすくなります。
「今回だけ」「少しなら」「誰にも迷惑をかけていない」
この“ゆるみ”が静かに扉を押し開けてしまいます。
④ 直後の安堵感
行動後の「落ち着く感覚」が脳に“報酬”として記録されると、次の衝動が強まります。
「繰り返される仕組み」はここで固まりやすくなります。
この4つの要素が重なることで
『やめたい気持ち』より『いつもの流れ』が勝つ
状態が作られます。
つまり“扉が勝手に開く”のではなく、
内側で少しずつ準備が進んでいく という構造です。
ここを理解しないまま「二度としません」と気持ちだけで抑えようとすると、
早い段階で限界が来てしまいます。
扉の“前”を支える ― 認知行動療法による再犯防止
認知行動療法(CBT)の再犯防止支援は、
「行動そのものを止める」というよりも、
扉が開く前段階で立ち止まれる仕組みを整えることを目的に進めます。
1.現状の整理
どのような場面・感情・時間帯・状況で“扉に近づきやすくなるか”を一緒に言葉にします。
見えないものを可視化することで「まだ開いてはいないけれど、いま近づきつつある」と気づける土台ができます。
2.考え方の立て直し
衝動の直前には、小さな自己正当化が起きます。
ここを“気づける形”にしておくことで、
「大丈夫」ではなく
「これは扉に手をかけ始めている段階かもしれない」
と認識することが可能になります。
3.衝動が強まったときの対応
最終段階で必要なのは“否定”ではなく“距離”です。
- その場から身体を離す
- 深い呼吸で落ち着かせる
- 強さを短く記録する
- 信頼できる相手に一言知らせる
これにより、扉を開ける前に時間を稼ぎ、“軌道”を外せます。
4.継続(やめ続けられる状態)
落ち着いている時期こそ油断が入りやすく、静かに扉へ近づく動きが始まることがあります。
そのため、
- 日々の状態をゆるやかに点検
- 危険な条件を遠ざける工夫
- 少しの不調も早めに共有
という「維持の仕組み」を支援の中で作っていきます。
“本人のため”だけではなく、“次の世代のため”でもある
NHKスペシャルのテーマにある
「子どもを守るには」
という問いは、「被害の子ども」だけを指しているわけではありません。
性犯罪の「扉」が無自覚のうちに開いてしまう構造を理解し、
その前で立て直す支援が当たり前に存在すれば、
将来、いまの子どもが“同じ扉”に手をかける可能性も下がります。
つまり再犯防止支援は、
“すでに起きた行動への対処”であると同時に
**“次の世代が同じ入口へ近づかないための予防”**でもあります。
加害行為は「個人の問題」ではなく、
“学習され、再生産されていくリスク”を持ちます。
だからこそ、扉が開く前を扱う支援には社会的な意味があります。
Q&A
Q1:まだ事件化していない段階でも相談できますか?
はい。行動に至る前段階(考え方・状態の整理)から対応可能です。
Q2:家族が相談することもできますか?
可能です。本⼈がまだ相談できない状況でも、ご家族側の理解と対応の整え方を支援します。
Q3:どのくらいの頻度で通うものですか?
固定ではありません。「状態の整理」「衝動への対処」「維持」のどこを扱うかにより異なります。
静岡浜松店へのご相談
【所在地】
〒430-0944 静岡県浜松市中央区田町231番地8 プレイスワン田町301号室
【受付時間】
10:00〜20:00(完全予約制)
【予約フォーム】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelm3nMBwOyvwnkhrkihe-APBzNTll2NL4fsPB6b6hHMzC8GA/viewform
【LINE】
https://lin.ee/26sKHRK8
【WEBサイト】
https://hamamatsu.cbt-mental.co.jp/
【NHK番組サイト】
https://www.web.nhk/tv/an/special/pl/series-tep-2NY2QQLPM3/ep/Y7Q5G96V8J
まとめ
性犯罪の再犯防止は、「行動そのもの」を扱うだけでは不十分です。
そのもっと手前の“扉が開き始める前”を見ていく視点が欠かせません。
今回のNHKスペシャルのテーマ
「加害の“扉”が開くとき 子どもを守るには」
は、当センターが日々向き合っている支援の現場と重なる内容です。
扉の前で立ち止まり、整え直すこと。
それは本人の人生を守るだけでなく、
これから育つ子どもたちが“同じ扉に手をかけない未来”をつくることにもつながります。